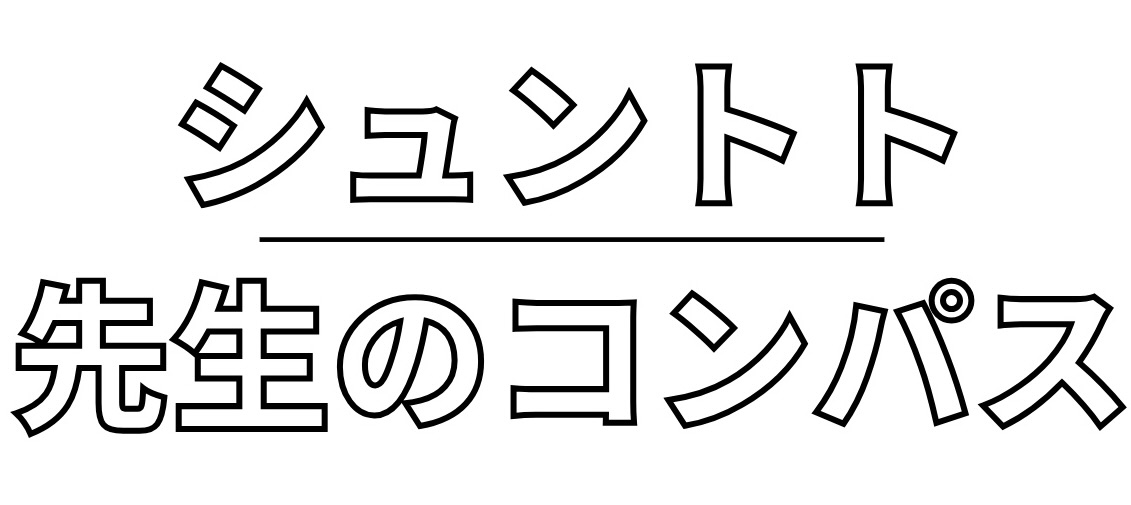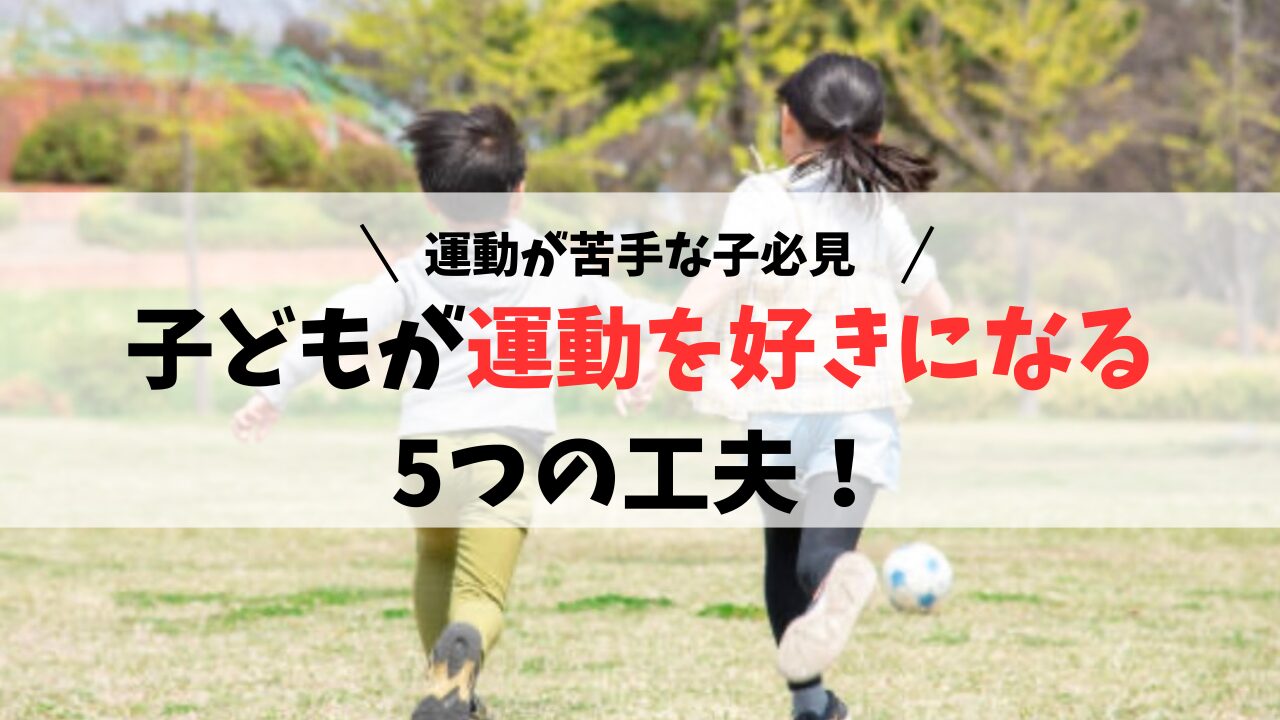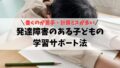目次
「うちの子、体を動かすのが苦手で…」
「体育の授業が嫌で、いつも気が重そう…」
そんなお悩みを抱える保護者の方、実はとても多いんです。
でも、運動が苦手な子に対して「もっと頑張って!」「走れば速くなるよ!」という声かけだけでは、逆効果になってしまうことも。
子どもが運動を好きになるためには、成功体験や楽しさを感じることが何よりも大切です。
そして、「運動嫌い」は努力不足じゃない!
この記事では、運動が苦手な子どもが、前向きに体を動かすようになるための5つの工夫をご紹介します。
運動嫌いを自信に変えるサポートを、家庭で始めてみませんか?
(家庭教師ファーストは運動が苦手な子へのやさしいマンツーマン指導が魅力!)
運動が苦手な子に共通するつまずきポイントとは?

運動が苦手な子に共通するつまずきポイントとは?
「うちの子、運動になると急に消極的になってしまうんです…」 「体育の時間がイヤで、朝から憂うつそうで…」
そんな風に、運動の話になると不安な気持ちを抱えてしまう保護者の方も多いのではないでしょうか。
運動が苦手な子には、実は共通するつまずきポイントがあります。
それは、「運動能力がない」からではなく、周りと比べられる不安や、うまくできなかった経験の積み重ねによって「自信をなくしている」ことが多いのです。
たとえば
- ボールを投げたらみんなに笑われてしまった
- 鉄棒で逆上がりができなくて、置いていかれる感じがした
- チーム競技でミスをして責められた
こうした経験が、「運動=嫌なもの」というイメージにつながってしまい、自然と体を動かすことから遠ざかってしまうのです。
また、発達特性や感覚の過敏さが影響しているケースも少なくありません。
たとえば、バランス感覚や空間認知が未熟な場合、ジャンプやボールのキャッチが難しく感じられたり、周囲の音や刺激に敏感で体育の授業がしんどい…ということもあります。
だからこそ、最初に知っておきたいのは、
運動が苦手=怠けている・やる気がないわけではない
ということ。
原因を知り、子ども自身の特性や感じている難しさに目を向けることが、運動を好きになる第一歩になります。
運動の苦手意識は、環境や声かけ、成功体験の積み重ねで必ず変わっていきます。
「うちの子にもできるかも」と思える瞬間が、次の「やってみたい」につながるんです!
小さな成功体験を積み重ねる

「うちの子、運動がとにかく苦手で…」
そんな悩みを抱えるママ・パパは、きっと少なくありません。
かけっこでいつもビリだったり、ボールが怖くてキャッチができなかったり。
そんな姿を見て、「このままで大丈夫かな」と心配になることもありますよね。
でも、大きな成長のカギは、「できた!」の小さな積み重ねなんです。
運動が苦手な子どもにとって、いきなり成功体験を得るのは難しいかもしれません。
だからこそ、「少しでもできたこと」を見逃さずにほめることがとても大切。
たとえば…
- 前より速く走れた
- ボールに少し触れられた
- 最後までルールを守って参加できた
どれも立派な一歩です。
運動に自信がない子は、「どうせ自分には無理」と思いがち。
その気持ちをくつがえすのが、成功体験の力です。
少しずつでも「自分にもできた」という感覚が育つと、運動に対するハードルがぐっと下がります。
小さな成功体験は、自己肯定感を育てる最高のツール。
「苦手を克服する」ことがゴールではなく、「自分って思ったよりできるかも」と思える瞬間を増やすことが、運動嫌いを克服する第一歩なんです!
成功体験を積ませて「やればできる!」という気持ちを育てよう

「どうせできないからやりたくない」「また失敗しそう…」
そんなふうに思ってしまうお子さんの心の奥には、過去の失敗体験や、「運動=自分には無理なこと」という思い込みがあるかもしれません。
でも、ほんの小さな「できた!」の積み重ねが、子どもの自信を大きく育ててくれるんです。
たとえば
- 昨日より少し遠くまで走れた
- 前はできなかった縄跳びが1回跳べた
- 一緒にやったストレッチが楽しかった
このような“小さな達成感”を親子で一緒に喜ぶことが、何よりの自信につながります。
大切なのは、
「結果」よりも「過程」や「気づき」に目を向けてあげること。
「すごいね!あきらめずにやってみたんだね」
「昨日よりちょっと速く走れたね、がんばったね」
そんな声かけが、運動に対するネガティブなイメージを少しずつ変えていきます。
また、競争や順位よりも自分のペースで挑戦できる環境を意識してあげると、プレッシャーが減って挑戦しやすくなります。
運動が苦手な子にとっては、「失敗しない」「誰かと比べられない」「笑われない」場所がとても大切です。
おうちの中や少人数の習いごとなど、安心してチャレンジできる空間を選んであげることもサポートのひとつです♪
親の関わり方ひとつで、子どもの運動嫌いは変わる

「うちの子、運動が嫌いみたいで…」
そう感じるとき、もしかしたらお子さんの“気持ち”に気づくチャンスかもしれません。
実は、運動そのものが嫌いというよりも、「苦手な自分を見られるのが恥ずかしい」「うまくできないことで自信を失っている」
そんな理由から距離を置いているお子さんも少なくありません。
だからこそ、親の声かけや関わり方がとても大切なんです。
たとえば、
- 「どうしてできないの?」よりも「頑張ってたね、見てたよ」
- 「もっと上手にやってごらん」よりも「昨日より少し速くなったね!」
こういった言葉の選び方ひとつで、子どもの心はグッと前向きになります。
また、親が無理に「やらせよう」とするよりも、一緒に体を動かしたり、失敗しても笑い合ったりする中で、自然と「楽しいな」という気持ちが育まれていくことも多いです。
子どもにとって、運動ができるかできないかよりも、楽しいか楽しくないかが大切な軸。
だからこそ、「結果」ではなく「過程」を認めてあげましょう。
運動は、苦手な子ほどちょっとずつが鍵!
親が「待つ姿勢」「寄り添う姿勢」を大切にすればするほど、子どもの中に小さな「やってみようかな」が芽生えていきます。
あなたの関わりひとつで、お子さんの世界が広がっていく。
そう思うと、今日のたった一言が未来への贈り物に思えてきますね♪
まとめ|「苦手」が「楽しい!」に変わるきっかけは、日常の中にある

「うちの子、運動が苦手で…」「体育の時間が憂うつみたいで…」
そんなお悩みを抱えている保護者の方に、今日お伝えしたかったのは、
運動の苦手は、努力不足ではなくきっかけ不足かもしれない
ということ。
運動の上手・下手は、決して生まれつきだけで決まるものではありません。
ちょっとした成功体験、ちょっとした工夫、ちょっとした“できた!の積み重ねが、
子どもの「運動って楽しいかも!」という気持ちを育ててくれます。
そして、何より大切なのは、
「うまくやること」よりも「前向きに向き合うこと」。
「今日も頑張ったね」「昨日よりちょっと上手だったね」
そんな声かけひとつで、子どもの心はぐっと軽くなります。
大きな一歩じゃなくていい。
小さな一歩、小さなチャレンジ、小さな成功を見つけていきましょう!
今日の笑顔が、明日の自信に変わるように。
保護者のあなたが寄り添いながら、お子さんと一緒に「楽しい運動」を見つけられますように。