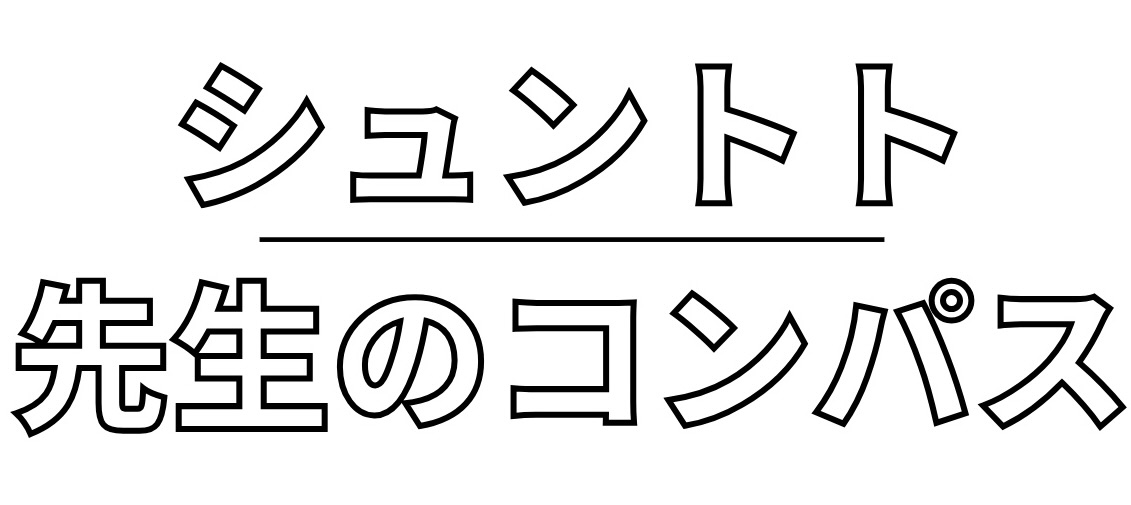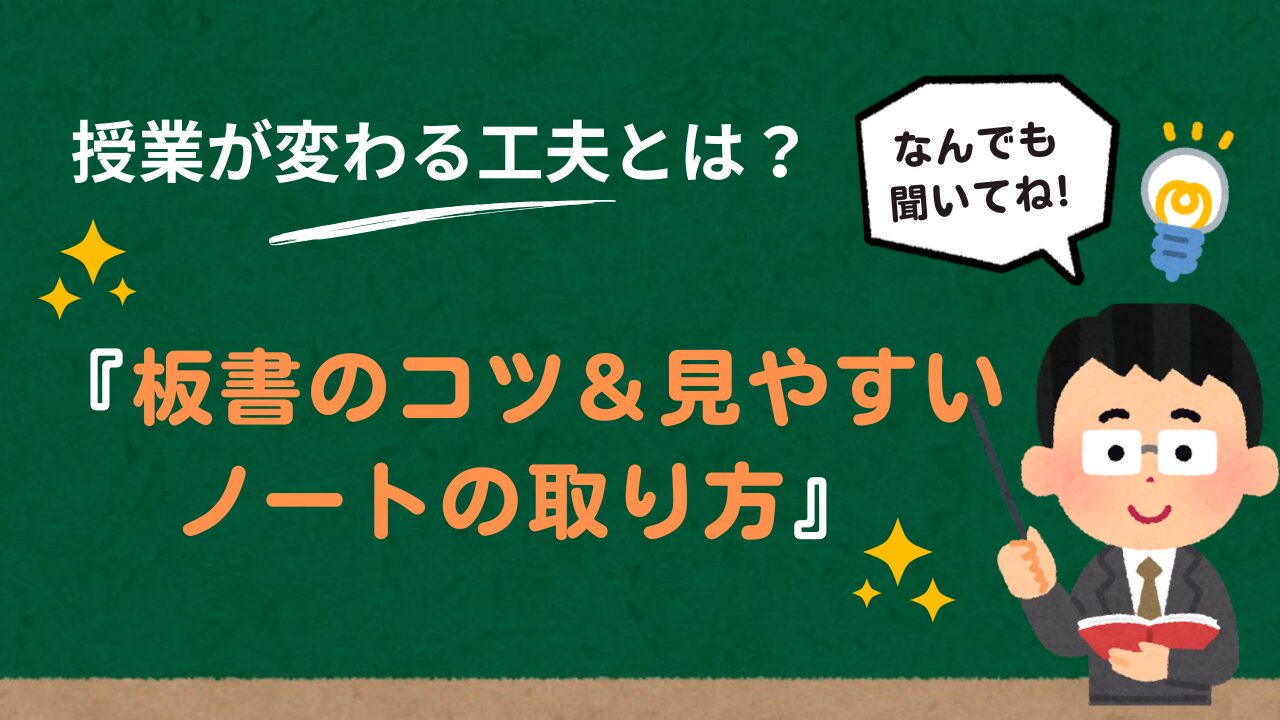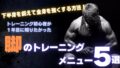目次
「授業の板書がうまくまとまらない…」
「生徒のノートをチェックすると、バラバラでわかりにくい…」
そんな経験はありませんか?
実は、「授業の板書」と「生徒のノート」は密接に関係しており、どちらか一方が乱れると、授業の理解度が下がることも…
本記事では、「見やすく整理された板書のコツ」と、「生徒に伝えたい、効果的なノートの取り方」を詳しく解説します!
板書が授業に与える影響とは?
「伝わる板書」と「伝わらない板書」の違い
◯伝わる板書 → 生徒が視覚的に理解しやすい!
◯ 伝わらない板書 → 情報が多すぎて、どこを見ればいいかわからない…
板書は、「授業の流れを整理し、視覚的に情報を伝える手段」です!
しかし、ごちゃごちゃした板書では、生徒が内容を理解しにくくなることも…。
✔️ 「どこが重要か、一目でわかる板書」が理想!
見やすい&わかりやすい板書のコツ!
「どんな板書なら、生徒が理解しやすくなるのか?」
ここでは、実践しやすい「板書のコツ」を紹介します!
板書のレイアウトを固定する!(3分割ルール)
授業ごとにバラバラな板書だと、生徒が混乱しやすい…!
そこでおすすめなのが、「3分割ルール」です!
◯ 左側 → 目標・キーワード・重要ポイント
◯ 中央 → 具体的な説明・図解
◯ 右側 → まとめ・練習問題・ポイント整理
✔️ 「レイアウトを固定するだけで、授業の流れがスムーズに!」
文字の大きさ・色分けを工夫する!
「文字が小さくて読めない…」
「重要な部分が目立たない…」
これを防ぐために、色分け&メリハリを意識!
◯大見出し → 白 or 黄色(チョーク or マーカー)
◯キーワード・重要ワード → 赤 or 青
◯補足・具体例 → 緑 or 水色
✔️「色を使いすぎると逆に見にくくなるので、3色までがベスト!」
板書の「書く順番」を工夫する!
「先生の板書が速すぎて、ノートを取るのが大変…」
こんな声が出ないように、「書く順番」を意識することが大切!
◯ おすすめの流れ
- まず「見出し」を書く → 何を学ぶのか明確に!
- 次に「ポイント」を書く → キーワード&要点を整理!
- 最後に「具体例」や「まとめ」を記入!
✔️ 「この順番を守ると、生徒がノートを取りやすくなる!」
生徒が理解しやすいノートの取り方を指導する方法
「先生が板書しても、生徒のノートがバラバラ…」
「見返しやすいノートを作らせたいけど、どう指導すればいい?」
こんな悩みを持っている先生も多いのではないでしょうか?
実は、ノート指導はただ「きれいに書く」ことが目的ではありません。
大切なのは、「学びを整理し、自分で活用できるノートを作ること!」
ここでは、生徒のノートを「学びの武器」にするための指導法を紹介します!
1ページを「見出し」「ポイント」「まとめ」に分ける!
生徒が自由にノートを取ると、
✅ 「ただ書き写すだけ」(思考が伴わない)
✅ 「情報が詰め込まれすぎて、後で見返しにくい」
✅ 「どこが重要かわかりにくい」
といった問題が起こりがち。
そこで、1ページを「3つのエリア」に分けるルールを設定することで、ノートが整理されます!
・ 左側(タイトル&キーワードエリア) → 板書の見出し・重要ワードを記録
・ 中央(メインエリア) → 授業の内容、説明、図解などを記録
・ 右側(まとめ&考察エリア) → 気づき・振り返り・疑問点を書き出す
◯ 授業後に振り返る際、「右側」だけを読めば、要点がわかる!
◯ 後から追加でメモを書き込めるので、発展的な学びにもつながる!
✔️「ノートは、後で見返しやすいように作ることが大事!」
重要ワードには線を引かせる!(強調ルールを作る)
生徒のノートを見ると、どこが大事なのかわかりにくい…
→ こんなときは、「強調ルール」を決めると、生徒が意識的にノートを整理しやすくなります!
・ 赤線 → 最重要ワード(覚えるべき単語)
・ 青線 → 理解のポイント(理由や考え方)
・ 黄色マーカー → 授業のキーポイント
✔️ 「全員が同じルールで強調すると、見返しやすいノートになる!」
色ペンを使いすぎない!(3色ルール)
「カラフルなノート = 見やすいノート」とは限りません!
むしろ、色が多すぎると 「情報過多で混乱」 してしまうことも。
◯ 「使う色は3色まで」に制限!
◯ 色の役割を決め、ルール化する!(例:赤=強調、青=補足、緑=考察)
✔️「シンプルにすることで、ノートが見やすくなる!」
余白を意識し、書き込みスペースを作る!
ギッシリ書かれたノートは、後で書き足せない…
→ そこで、ノートの余白を意識的に残すことを指導!
・右側に「後で追記するスペース」を確保(授業後に振り返りや補足を追加!)
・ページの下部に「考えたこと・疑問を書くエリア」を作る
・ノートの間に付箋を挟めるスペースを意識!
✔️ 「余白=学びの発展スペース!」
板書とノートを連携させる指導アイデア
ノートをうまく取れるようになっても、
◯「授業中に書くべき部分がわからない…」
◯「ノートを活用する習慣がない…」
という生徒もいます。
そこで、板書とノートを連携させる工夫を加えることが重要!
「ここはノートに書こう!」と明確に指示を出す!
◯先生が話したことをすべてノートに書く必要はない!
→ どこが重要かを明確に伝えることが、ノート指導のカギ!
・ 「今から書く部分は、ノートの”ポイントエリア”にメモして!」
・ 「この単語は絶対に書こう!試験に出るぞ!」
・ 「ここは自分の言葉でまとめてみよう!」
✔️「板書とノートの内容を一致させると、学習効果がUP!」
「ペアでノートを見せ合う時間」を設ける!
◯「他の人のノートを見ると、自分のノートの改善点がわかる!」
◯ 「書き方の工夫をシェアすることで、ノートの質が向上!」
・「3分間で、お互いのノートを見て、良いポイントを見つける」
・ 「ノートの工夫をクラスで発表!」
✔️ 「ノートをオープンにすることで、学びの幅が広がる!」
「授業の最後に、ノートを見返す時間を作る!」
◯「ノートは書いたら終わり」ではなく、「見直すことが大事!」
◯ 授業の最後の3分間で、「今日のノートの振り返り時間」を作る!
・「今日の授業で、一番大事だったことを1行でまとめる!」
・「疑問に思ったことをノートの余白に書く!」
✔️ 「ノートを”使う”ことで、学びが定着する!」
まとめ|板書とノートを工夫して、授業の質を高めよう!
✅ ノートの取り方を指導すると、生徒の学びが深まる!
✅ 「板書とノートを連携」させることで、学習効果が向上!
✅ ペアワーク&振り返りを取り入れ、ノートを活用する習慣を作る!
板書×ノート=学びの質が変わる!
ぜひ、今日から実践してみてください!