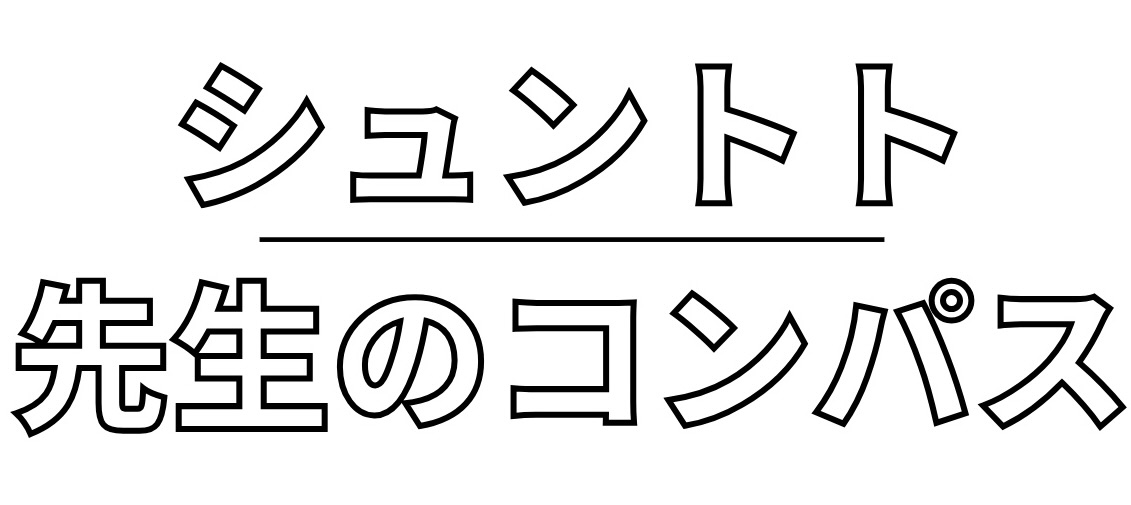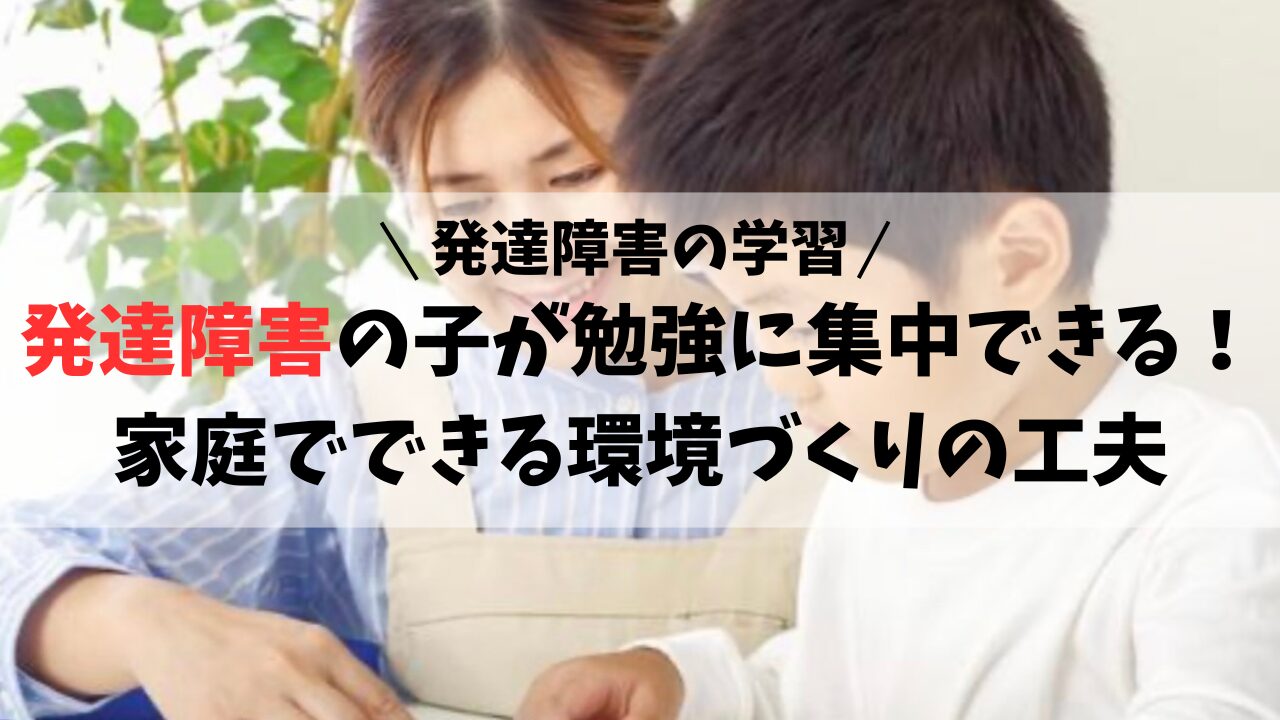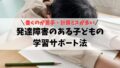目次
「うちの子、なかなか勉強に集中できなくて…」
こんなお悩みを抱えている親御さんは多いのではないでしょうか?
特に、ADHD・ASD・LDなどの発達特性を持つお子さんは、一般的な学習スタイルでは集中しづらいことがあります。
でも、大丈夫です!
お子さんの特性に合わせて学習環境を少し工夫するだけで、
「気が散りにくい」「学習に取り組みやすい」空間を作ることができます。
本記事では、発達障害の子どもが集中しやすくなる学習環境の作り方をご紹介します。
すぐに実践できる工夫もたくさんお伝えするので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪
どうしてうちの子は集中できないの?発達障害の子どもが気が散りやすい理由

「机に向かってもすぐに立ち歩いてしまう」
「宿題を始めても、気づいたら別のことをしている」
このような悩みを抱えている親御さんも多いのではないでしょうか?
発達障害(ADHD・ASD・LD)を持つお子さんは、もともと集中力のコントロールが難しい特性を持っています。
決して「やる気がない」「怠けている」わけではなく、脳の働き方が少し違うだけなんです。
では、なぜ発達障害の子どもは学習に集中しづらいのでしょうか?
ここでは、その理由を詳しく見ていきましょう。
ADHD(注意欠如・多動症)の場合:気が散りやすく、じっとしていられない
ADHDの子どもは、脳の「注意をコントロールする機能」が弱いため、 周囲の刺激に敏感に反応してしまいます。
例えば、
- 窓の外で鳥が飛んでいるのが気になる
- おもちゃが視界に入ると、つい手に取ってしまう
- 机に向かっても、数分後には別のことを考えてしまう
このように、外部の刺激によって集中が途切れやすいのが特徴です。
また、「じっとしているのが苦手」という特性もあり、長時間同じ姿勢でいることが難しいお子さんもいます。
ASD(自閉スペクトラム症)の場合:環境の変化が苦手で、特定のこだわりがある
ASDの子どもは、「自分のペース」や「こだわり」が強いことが多く、学習環境が少しでも変わると落ち着かなくなることがあります。
例えば、
- いつもと違う場所で勉強すると、不安になって集中できない
- 音や光に敏感で、環境音(時計の秒針やエアコンの音)に気を取られる
- 自分なりのやり方にこだわりがあり、指示された方法で勉強するのが難しい
「周囲の変化がストレスになりやすい」という特性があるため、学習環境を整えることが特に大切になります。
LD(学習障害)の場合:読み書きや計算が苦手で、学習そのものが負担に
LD(学習障害)を持つお子さんは、特定の学習分野に困難を抱えることが多いです。
- 文字を読むのが苦手で、文章を理解するのに時間がかかる
- 書くことが苦手で、ノートをとるのが大変
- 数字をうまく認識できず、計算がスムーズにできない
このように、「学習自体がとても疲れるもの」と感じてしまうため、長時間勉強に向き合うことが難しくなります。
発達障害の子どもが集中できないのは、 本人の努力不足ではなく、脳の特性によるものです。
「どうしてうちの子は勉強に集中できないんだろう…」と悩んでしまうこともあるかもしれませんが、お子さんの特性を理解し、適切な環境を作ることで、集中しやすくなることも多いです。
次の章では、発達障害の子どもが 「自分から勉強に取り組める」環境づくりの工夫を紹介していきます!
【ポイント:視覚的にわかりやすく、ステップアップ式なので、学習が苦手な子でも取り組みやすい】
環境を変えれば集中力がアップ!発達障害の子が落ち着いて勉強できる3つの工夫

お子さんが勉強に集中できないと、「どうしたら落ち着いて学習できるんだろう?」と悩むこともありますよね。
でも、実は学習環境を少し整えるだけで、驚くほど集中しやすくなることがあります!
発達障害(ADHD・ASD・LD)を持つ子どもは、周囲の環境から受ける影響がとても大きいです。
逆に言えば、「勉強しやすい環境」を作ることで、自然と学習に向かいやすくなるんです。
ここでは、 お子さんが落ち着いて勉強に取り組める3つの工夫をご紹介します!
余計なものを減らし、シンプルな学習スペースを作る
発達障害の子どもは、目や耳から入る情報に敏感なことが多く、視界に余計なものがあると、すぐに気が散ってしまうことがあります。
おすすめの環境づくり
・ 机の上は最小限に(筆記用具・教科書・ノートだけ)
・ 学習スペースの壁はシンプルに(カラフルなポスターやおもちゃは視界に入れない)
・ 整理整頓しやすい収納を用意する(「片付けが苦手」なお子さん向けに、簡単にしまえるボックス収納が◎)
「子ども部屋では勉強に集中できない…」という場合は、リビングの一角を学習スペースにするのもおすすめです。
「親の気配が感じられる」「適度に見守られている」と感じることで、安心して学習に向かえるお子さんも多いですよ。
音や光の刺激を調整し、落ち着ける環境を作る
「周りの音が気になって勉強に集中できない…」
これは、ADHDやASDの子どもによくある悩みの一つです。
例えば、
- 家族の話し声が気になる
- テレビの音が聞こえるとそちらに注意が向いてしまう
- 窓の外の車の音や、時計の秒針の音が気になる
このような刺激を減らすために、静かで落ち着ける場所を学習スペースにすることが大切です。
おすすめの対策
・ ホワイトノイズマシンや耳栓を活用する(無音が苦手な子には、心地よい自然音やBGMを)
・ 明るさを調整できるデスクライトを使う(蛍光灯の光がまぶしすぎると、疲れやすい子も)
・ パーテーションを活用する(視覚的な刺激を減らすだけで、集中しやすくなることも)
「家の中で静かな場所がない…」という場合は、 図書館や学習スペースを活用するのも◎
お子さんが「ここなら落ち着いて勉強できる」と思える場所を、一緒に探してみてくださいね。
こまめに休憩を入れ、「頑張れるリズム」を作る
発達障害の子どもは、「一度集中が切れると、再び学習に戻るのが難しい」ことがあります。
逆に、長時間座りっぱなしだと疲れてしまい、かえって学習効率が下がることも…。
そんなときにおすすめなのが、 「ポモドーロ・テクニック」という学習法です!
これは、25分勉強+5分休憩というサイクルを繰り返す方法で、短時間で集中力を最大限に高めることができます。
おすすめの学習リズム
・ 小学生なら「15分勉強+5分休憩」から始める
・ タイマーを使って、ゲーム感覚で取り組む
・ 休憩時間にはストレッチや軽い運動を取り入れる
「ずっと座っているのが苦手」なお子さんには、立ったまま学習できるハイデスクやバランスボールチェアを取り入れるのも◎。
少し動きながら学ぶことで、集中しやすくなることもありますよ!
発達障害の子どもが学習に集中できるかどうかは、 環境によって大きく変わります。
「勉強しなさい!」と叱るよりも、 「集中しやすい環境づくり」に目を向ける ことで、お子さんが自分から学習に取り組めるようになります。
次の章では、 「学習のやる気を引き出す工夫」 について詳しくご紹介します!
【ポイント:「時間の見える化」はADHDの子どもに特に効果的!自分のペースで学習できる環境づくりに◎】
子どもが自然と勉強に向かう!集中力を引き出す学習スペースの作り方
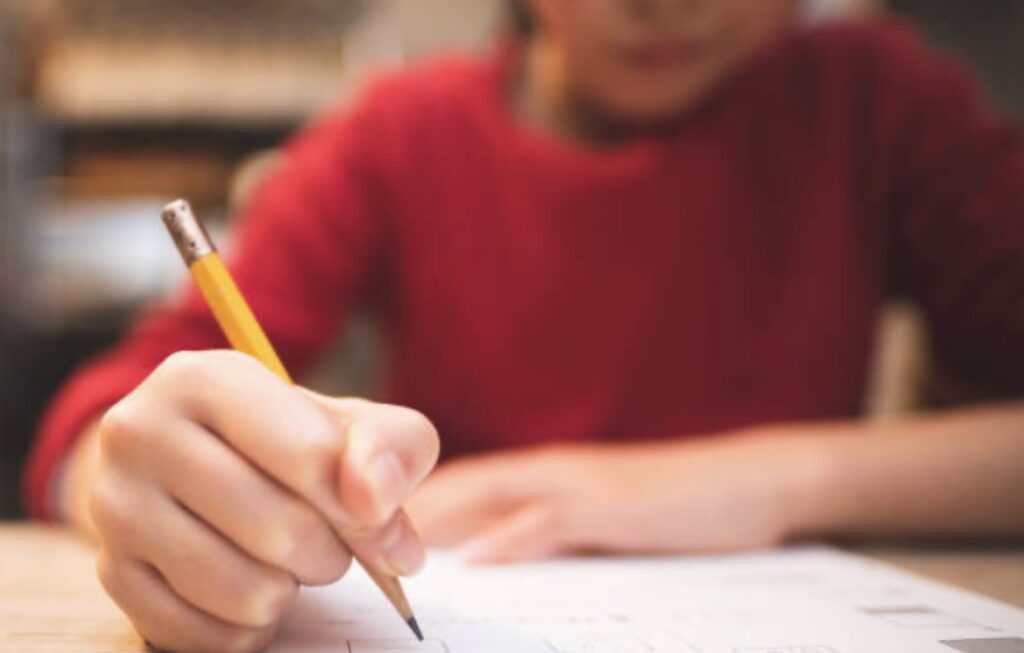
「勉強しなさい」と言わなくても、お子さんが自分から机に向かうようになったら嬉しいですよね。
実は、ちょっとした 学習スペースの工夫で、そんな理想の環境を作ることができるんです。
発達障害の子どもは、「環境のちょっとした違い」で集中できるかどうかが大きく変わることがよくあります。
逆に、「うちの子は勉強に集中できない…」と感じる場合、もしかしたら 学習環境が合っていない可能性も。
ここでは、 お子さんの特性に合わせて、集中しやすい学習スペースを作るための具体的な工夫をご紹介します!
机と椅子の高さをお子さんに合わせる
学習に集中できるかどうかは、実は「座りやすさ」 にも大きく関係しています。
もし、今使っている机や椅子が お子さんの体に合っていない場合、それだけで集中しにくくなってしまうことも。
適切な机と椅子のポイント
・ 足がしっかり床につく高さに調整する(足がぶらぶらすると落ち着きにくい)
・ ひじが90度になる高さの机を選ぶ(高すぎると疲れやすく、低すぎると猫背に)
・ クッションやフットレストで微調整する(高さが合わないときの対策)
「うちの子、すぐに姿勢が崩れる…」という場合は、座面が少し傾斜した椅子やバランスボールチェア を試してみるのもおすすめ!
姿勢をキープしやすくなると、自然と集中しやすい環境が整いますよ。
お子さんに合った「視覚的な刺激」を調整する
発達障害の子どもは、周囲の視覚的な刺激に敏感なことが多く、「目に入るもの」によって集中力が大きく左右されることがあります。
例えば、
- 机の周りにポスターやカレンダーがたくさん貼ってある
- 本棚がぎっしり詰まっていて、気になってしまう
- おもちゃが見える場所に置いてある
このような環境では、どうしても気が散ってしまいやすいですよね。
そこで、「シンプルで落ち着ける学習スペース」を意識して整えてみましょう!
視覚的な刺激を減らす工夫
・ 机の正面には何も置かず、無地の壁にする(シンプルな色の壁紙も◎)
・ 本棚にはカーテンや扉をつけて、視界に入らないようにする
・ おもちゃは学習スペースの外に置くか、収納ケースにしまう
特に 「視界にあるものがすぐに気になってしまう」タイプのお子さんには、
パーテーションや仕切りを活用するのもおすすめです!
勉強に集中する時間と、リラックスする時間の 「メリハリ」 をつけることが大切です。
「音の刺激」に配慮し、集中しやすい環境を作る
発達障害の子どもは、聴覚が敏感で、ちょっとした音にも気を取られやすいことがあります。
例えば、
- 兄弟の話し声やテレビの音が気になる
- 外の車の音や、雨の音で集中できない
- 時計の針の音や冷蔵庫のモーター音まで気になる
こうした場合は、「音の刺激を調整する工夫」 を取り入れるのがおすすめです!
音環境を整える工夫
✔️ 耳栓やノイズキャンセリングヘッドホンを活用する
✔️ ホワイトノイズマシンで気になる音を打ち消す(川のせせらぎや雨音など)
✔️ カフェミュージックや環境音BGMを流す(無音が苦手な子には特に効果的!)
「静かすぎると逆に落ち着かない…」という場合もあるので、お子さんに合った音環境 を一緒に探してみてくださいね!
学習スペースを整えることで、発達障害の子どもでも 無理なく勉強に集中できる環境 を作ることができます!
お子さんの特性に合わせた環境を作ることで、「勉強しなさい」と言わなくても、自然と学習に向かいやすくなるかもしれません。
次の章では、「学習習慣を定着させるコツ」について詳しくご紹介します!
【ポイント:視覚・聴覚を活かした教材設計で、特性に合わせたアプローチが可能】
無理なく続く!集中力を育てる習慣と毎日のサポート法

「集中力が続かない…」
「机には向かうけど、すぐにほかのことに気がそれちゃう…」
そんなお悩みを抱える保護者の方、多いのではないでしょうか?
発達障害のあるお子さんは、自分で集中を維持するのが難しいことが多く、何かに取り組んでいてもつい他の刺激に気を取られてしまうことがあります。
でも、焦らなくて大丈夫。ちょっとした習慣づけや、大人のさりげないサポートで、少しずつ「集中しやすい力」を育てることはできるんです。
この章では、忙しい日々の中でも取り入れやすい、集中力を高めるための習慣やサポートのコツをご紹介します。
ルーティンを作って「学習モード」にスイッチを入れる
発達障害のあるお子さんには、予測できる毎日の流れ=ルーティンがとても効果的です。
「これをしたら次は勉強」というように流れが決まっていると、脳が自然と学習モードに切り替わっていきます。
▼例:家庭で取り入れやすい学習前ルーティン
- おやつを食べる → トイレ → 机に向かう
- 好きな音楽を1曲だけ聴いてからスタート
- 勉強前に5分のストレッチや深呼吸をする
お子さんと一緒に「うちだけのルーティン」を決めると、自分で切り替える力も育ちますよ。
タイマーを使って“短時間集中”を習慣化
「集中が長く続かない…」というお子さんには、最初から長時間やらせようとしないことが大切です。
おすすめなのは、「○分だけやって、終わったら好きなことをしてOK」というスタイル。
たとえば、
- 最初は 5分だけ集中 → 1〜2分休憩 → また5分
- 慣れてきたら 10分 → 5分休憩 に伸ばす
こうすることで、お子さん自身が「短い時間ならがんばれる!」という 成功体験を積み重ねていくことができます。
タイマーやアプリを使うとゲーム感覚になり、楽しみながら取り組める子も多いですよ。
ごほうびシステムでモチベーションUP
発達障害のある子は、“やる気スイッチ”が見つかりにくいことがあります。
そんなときは、小さなごほうびで「できた!」の積み重ねをしていくのがおすすめです。
▼おすすめのごほうびアイデア
- 勉強が終わったら好きなシールを1枚貼る
- ポイントが貯まったらお気に入りのお菓子やお出かけ
- タイマーが鳴ったらガチャガチャ風のお楽しみボックスを開ける
大事なのは、「結果」ではなく「やろうとしたこと」を褒めること。
「机に向かえたね」「5分がんばれたね」と、プロセスを認める声かけが、お子さんの自信につながっていきます。
親が「見守るスタンス」でいることも大切
学習中、つい「ちゃんとやってる?」「集中して!」と声をかけたくなってしまいますよね。
でも、声かけが多すぎると、かえって集中を妨げてしまうことも…。
特に発達障害のお子さんは、言葉の刺激にも敏感なことがあるため、親がそばにいるだけでも緊張することがあります。
おすすめなのは、「近くにいるけど、必要以上に関与しない」見守りスタンス。
お子さんが安心して、自分のペースで取り組めるような「空気感」を意識してみてください。
たとえば、
- 同じ空間で自分の作業をして見守る
- 声をかける前に「目を合わせて」合図だけにする
- 頑張った後は、笑顔で「ありがとう」と伝える
「見守ってもらってる安心感」があると、子どもは不思議と落ち着き、少しずつ自立していくものです。
すべてを一度に完璧にする必要はありません。
できそうなところから少しずつ、親子で工夫を重ねていければ、それだけで大きな前進です。
「集中できないのはダメなこと」ではなく、「集中しやすくするための工夫を一緒に見つけていこうね」というスタンスが、きっとお子さんの力になりますよ。
【ポイント:親のストレス軽減、子どもの特性理解に役立つ内容が人気】
集中力UPと学びを支える!発達障害の子におすすめの学習ツール&教材

発達障害のお子さんに合う教材を探すとき、「どれが本当にうちの子に合うんだろう…」
と迷ってしまうことはありませんか?
市販の教材やアプリはたくさんありますが、大切なのは、お子さんの特性や好みに合った“使いやすさ”と“続けやすさ”。
この章では、「集中が続きやすい」「取り組みやすい」「楽しく学べる」という視点から、発達障害(ADHD・ASD・LDなど)のお子さんにおすすめの教材やツールを、いくつかご紹介します。
どれも実際に保護者や支援者の声が多いものなので、参考にしていただけたら嬉しいです!
視覚的にわかりやすい教材:絵・色・構造がポイント
発達障害の子どもたちは、文字だけの情報よりも、視覚で捉えられる情報の方が理解しやすい場合が多いです。
- 「くもんの学習ポスター」:ひらがな・カタカナ・九九など、目に入る場所に貼って自然に覚えられる
- 「Gakkenニューブロックドリル」:パズル感覚で学べて、空間認知や手先の発達にも◎
視覚を使って学ぶことで、学習のハードルがグッと下がり、成功体験につながりやすくなります。
ゲーム感覚で楽しく学べるアプリ&オンライン教材
「机に向かって勉強するのが苦手…」というお子さんには、アプリやタブレット学習がとてもおすすめです。
- スマイルゼミ(発達支援モードあり)
学習内容が視覚的に整理されていて、ナビゲーションもシンプル。ADHDやASDの子でも操作しやすいと評判です。 - NHK for School(無料)
短い動画で理解できる学習コンテンツが豊富。特に聴覚優位や視覚優位タイプのお子さんに人気です。 - Studyplus for School(スタディプラス)
勉強時間を「見える化」して、目標に向けてモチベーションを保ちやすい設計です。記録好きな子に◎
タブレットやスマホを使うことに罪悪感を感じる方もいますが、ツールとして上手に取り入れれば、むしろ「やりたい!」という気持ちを引き出すチャンスにもなります。
感覚統合や発達をサポートするアイテムも◎
学習そのものに集中するためには、身体的な感覚の調整(=感覚統合)も大切です。
- バランスボールやクッションチェア
座っているときに「ちょっと揺れる」「動ける」ことで、体幹が安定し、集中しやすくなることがあります。 - フィジェットトイ・ハンドスピナーなどの手遊びアイテム
「手を動かすことで落ち着く」お子さんに。授業中や学習中に手元に置いておくだけでも安心材料になります。
こうしたアイテムは、「落ち着いて学ぶ土台づくり」に役立ちます。子どもが安心できる環境=学びやすい環境です。
使う前に「一緒に選ぶ」ことが成功のカギ
教材やツールを選ぶときに大切なのは、「これ、やってみたい!」というお子さん自身の気持ち。
どんなに良い教材でも、「やらされてる感」があると続きません。
ですので、購入前や導入前に、お子さんと一緒に選ぶことをおすすめします。
例えば、
- 「これとこれ、どっちが好き?」と聞いてみる
- 実際に触ってから決められる体験会やサンプルを使う
- お子さんが好きなキャラクターのものを選ぶ
「自分で選んだ!」という感覚は、学習へのモチベーションにつながる大切な一歩になりますよ。
発達障害のあるお子さんには、一人ひとりに合った学び方・環境作りが何より大切です。
おすすめのツールはあくまで「ヒント」。
実際には、お子さんの「今」に合わせて柔軟に取り入れることが成功のコツです。
焦らず、比べず、お子さんと一緒に「楽しく続けられる学び」を見つけていきましょう!
【ポイント:視覚的にわかりやすく、ステップアップ式なので、学習が苦手な子でも取り組みやすい】
まとめ|発達障害の子どもが“自分らしく”学べる場所づくり

いかがでしたか?
発達障害のあるお子さんの学びを支えることは、ときに不安や戸惑いがつきまとうものです。
「これで合ってるのかな?」「うちの子だけ遅れてるんじゃ…」と悩む日も、きっとあると思います。
でも、忘れないでほしいのは、「子どもは一人ひとりちがっていていい」ということ。
そして、お子さんにとって“安心して過ごせる学びの場”をつくろうとしているあなたの姿こそが、何よりの支えです。
今回ご紹介した環境づくりの工夫やおすすめ教材は、あくまでスタート地点。
大切なのは、日々のお子さんの様子に寄り添いながら、「その子に合ったやり方」を一緒に見つけていくプロセスです。
たとえ小さな一歩でも、お子さんと一緒に踏み出せたなら、それは大きな成長のはじまり。
このブログが、少しでもそのお手伝いになれば幸いです。
あなたとお子さんのペースで、大丈夫です。
これからも一緒に、子どもたちの「自分らしく学べる力」を育んでいきましょう。