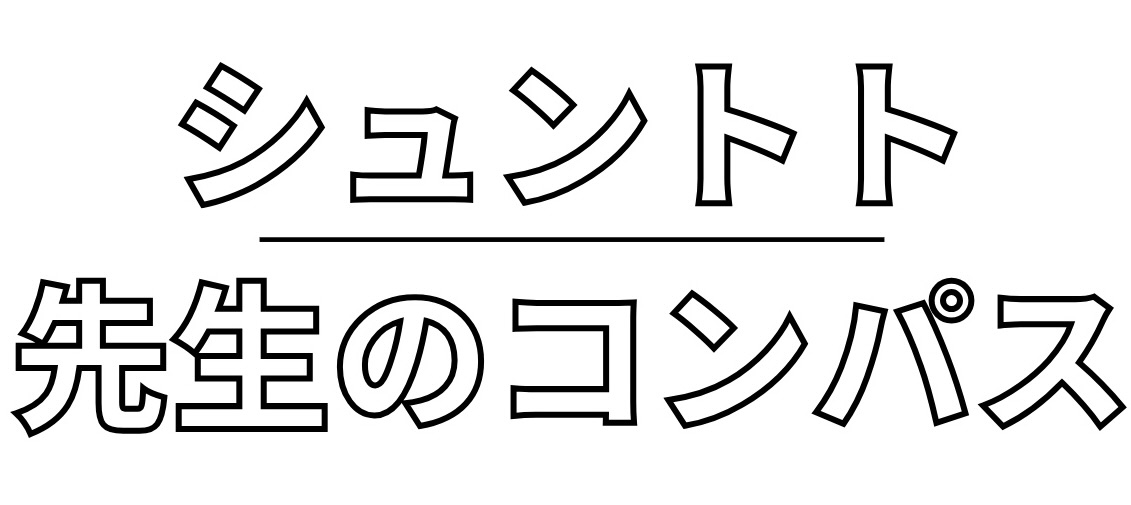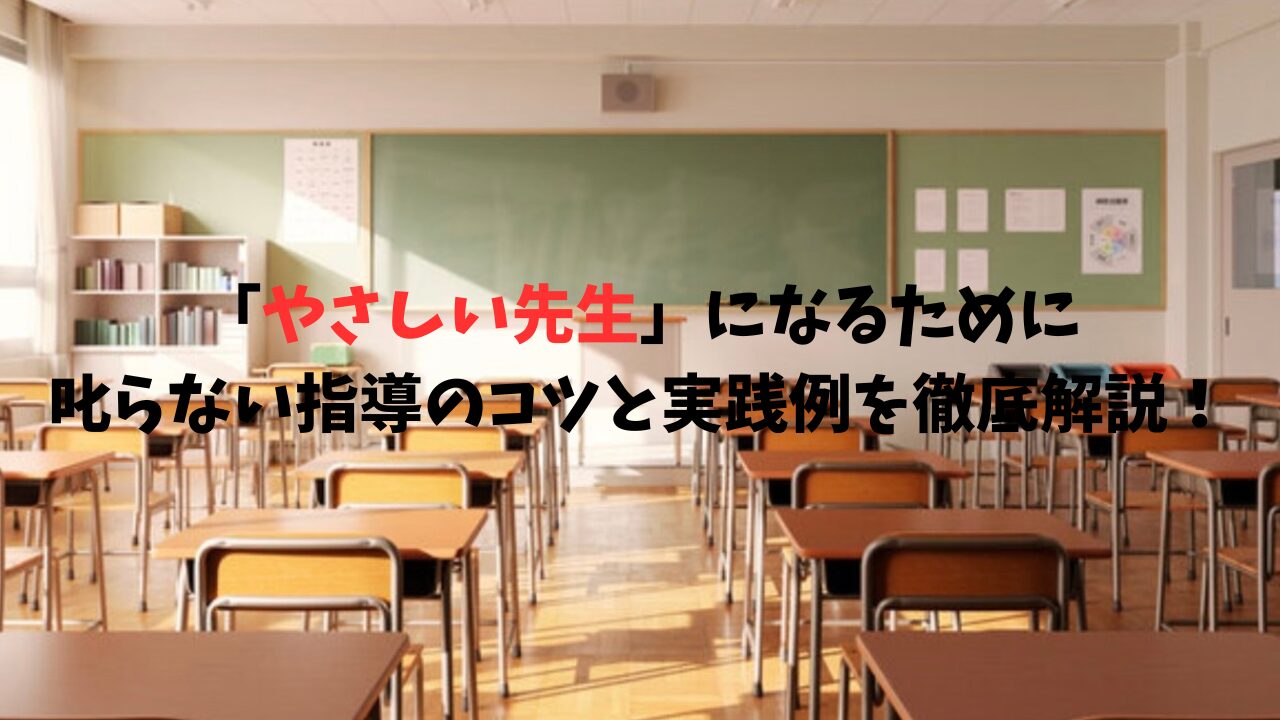目次
「もっとやさしく子どもに接したいのに、つい強い口調になってしまう……」
「叱るたびに自己嫌悪。どうすればいいんだろう?」
先生という立場にいると、毎日、子どもたちに向き合う中で
「叱るべきか、見守るべきか」迷う場面、たくさんありますよね。
でも、安心してください。
やさしい先生になろうと願っている時点で、
あなたはすでに子どもたちにとって素晴らしい存在です。
叱らずに指導することは、決して「甘やかす」ことではありません。
子どもたちの内側から「育とうとする力」を引き出してあげること。
この記事では、
- 叱らない指導がなぜ大切なのか
- やさしく、でも確実に成長を促すコツ
- 現場で使える具体例
を、わかりやすく紹介していきます。
小さな積み重ねが、子どもたちとの信頼を育み、
あなた自身も「指導が楽しい!」と思える毎日につながっていきますよ♪
一緒に、「叱らない指導」で未来を育てる一歩を踏み出していきましょう。
「やさしい先生」とは?子どもに伝わる本当の優しさ

「やさしい先生になりたい」
「子どもたちに信頼されたい」
そんなふうに思いながらも、現場ではつい叱ってしまったり、厳しい態度を取ってしまったり……。
先生自身も、心の中で葛藤していること、きっとありますよね。
子どもたちにとっての「やさしい先生」とは、
ただニコニコして何でも許してくれる存在ではありません。
本当に「やさしい先生」とは、子ども一人ひとりに向き合い、
必要なときにはしっかりと支え、時には厳しさも込めて見守ってくれる存在です。
叱らずに指導することは、単に甘やかすことではなく、
「どう伝えたら子どもが自分から気づき、成長できるか」を考える、
深い愛情と技術が求められるアプローチ。
だからこそ、叱らない指導にはコツと練習が必要なんです。
この記事では、
「叱る」よりも「導く」
そんなやさしい指導スタイルを身につけたいあなたに向けて、
具体的なコツと実践例をわかりやすく紹介していきます。
焦らず、完璧を目指さなくて大丈夫。
あなたが「子どもたちと真剣に向き合いたい」と願うその気持ちが、すでに第一歩なんです。
一緒に、子どもたちが心から安心できる教室づくりを目指していきましょう!
叱らない指導が子どもに与えるポジティブな効果|やさしい先生を目指そう

「叱らないなんて、甘やかしているだけじゃないの?」
そんなふうに感じる方もいるかもしれません。
でも、叱らない指導は決して甘やかしではなく、
子どもたちにとって大きな「安心」と「自信」を育てる大切な関わり方なんです。
特に小学生くらいの子どもたちは、まだまだ自己肯定感が育っている途中。
強く叱られることで、「どうせ自分はダメなんだ」という思い込みを持ってしまうこともあります。
逆に、叱らずに「どうしたらよかったかな?」「次はこうしてみよう!」と声をかけることで、
子どもたちは「失敗してもやり直せる」「挑戦しても大丈夫なんだ」という気持ちを持つことができるんです。
叱らないことで得られる3つのメリット
1. 自己肯定感が育つ
失敗を叱られるのではなく、チャレンジを認めてもらう経験は、
「自分はできる」「大丈夫」という自信に繋がります。
2. 自分で考える力がつく
「なぜダメだったのか」「次はどうすればいいか」を自分で考える時間を持たせることで、
指示待ちではない主体的な行動ができるようになります。
3. 大人との信頼関係が深まる
叱るよりも一緒に考え、寄り添う関わり方をすると、
「先生(親)は味方なんだ」と安心できるため、困ったときに相談しやすくなります。
叱らない=放置ではありません。
子どもたちが「もっと成長したい」と思えるような温かいサポートこそが、
やさしい指導につながります。
次の見出しでは、叱らずに伝えるコツについて具体的なテクニックを紹介していきますね。
叱らずに伝える!効果的な声かけ・コミュニケーション例

子どもたちに伝えたいことがあるとき、
つい「怒る」ことで伝えようとしてしまう場面、ありますよね。
でも実は、「叱らずに伝える」ほうが、子どもたちは驚くほど素直に耳を傾けてくれます。
ここでは、現場でもすぐ使える、やさしい先生になるための声かけ例を紹介します!
「ダメ!」ではなく、「こうしようね」と提案する
たとえば、教室内を走り回ってしまった子に、
つい「走っちゃダメ!」と強く言いたくなります。
でもそこで少しだけ視点を変えてみましょう。
「歩いて移動すると安全だよ。みんなが安心できるね」とポジティブな行動を提案することで、
子どもは「自分はこうすればいいんだ」と理解しやすくなります。
感情ではなく「行動」にフォーカスする
子どもの行動を注意するとき、人格を否定してしまうと自己肯定感を傷つけます。
たとえば、「あなたはだらしないね」ではなく、
「プリントを出すのを忘れちゃったね。次はどうしたらいいと思う?」と
具体的な行動に目を向ける声かけが大切です。
これにより、叱る代わりに「改善策を一緒に考える」雰囲気をつくることができます。
「できたこと」にしっかり目を向ける
指導というと「できていないこと」を指摘しがちですが、
できたことを見つけて褒めるのも、やさしい先生の大事なスキル。
「静かに話を聞けていたね」「優しく友達に貸してあげたね」と、
行動を具体的に言葉にして認めることで、
子どもたちは「もっと頑張ろう」と前向きな気持ちになれます。
実践!叱らない指導の現場例【学級経営・授業・トラブル対応】
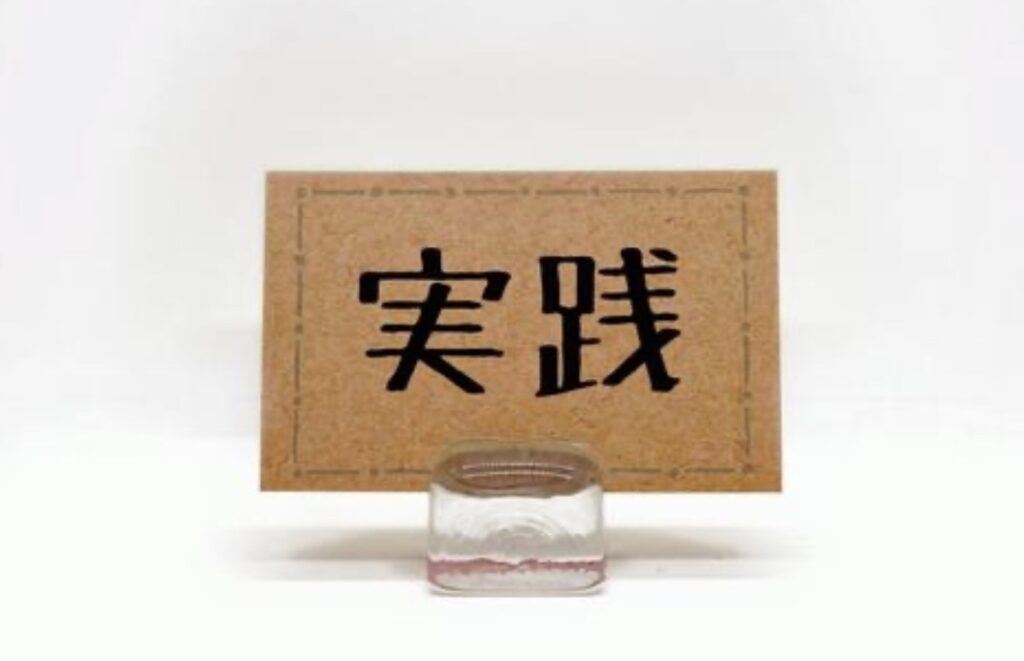
「叱らずに指導する」
頭ではわかっていても、実際の現場ではなかなか難しいですよね。
子どもたちは、想定外の行動をしたり、時には小さなトラブルを起こしたり。
でも、そんなときこそ、先生の対応が子どもたちの成長を大きく左右します。
ここでは、実際に私や周りの先生たちが現場で行っている
「叱らない指導」の工夫をご紹介します。
「自分にもできそう!」と感じてもらえるよう、具体例を交えてお伝えします!
【学級経営】注意より「仕組みづくり」で予防する
朝の会で「今日の目標」を一緒に決めたり、ルールをみんなで話し合って決めたりすると、
子どもたちは自分ごととして意識できるようになります。
例えば、忘れ物が多い子に対しても、叱るのではなく
「明日は忘れないためにどうしようか?」と一緒に作戦を立てる。
責任感や主体性を育てるチャンスになります。
【授業】間違いを責めず、チャレンジを称える
授業中に子どもが間違えたとき、すぐに正解を教えるのではなく、
「いい考えだね!ここは惜しかったね」とポジティブに受け止める声かけを心がけています。
「間違えてもいいんだ」という安心感が、次のチャレンジにつながります。
子どもの自己肯定感を育てる授業づくり、とても大切です。
【トラブル対応】「まず気持ちを受け止める」が第一歩
ケンカやトラブルが起きたときは、すぐに叱るのではなく、
まずどちらの気持ちもじっくり聞くことを大切にしています。
「怒ってたんだね」「悔しかったんだね」と感情を言葉にして代弁してあげることで、
子どもたちは落ち着き、自分の行動を振り返ることができるようになります。
そのうえで、「どうしたら次はうまくいくかな?」と一緒に考えていきます。
叱るより、寄り添う。
これが信頼関係を深める一番の近道です。
叱らない指導は、一朝一夕でできるものではありません。
でも、小さな積み重ねが確実にクラスの空気を変え、子どもたちを伸ばしていきます。
「完璧じゃなくていい」「まずはひとつでも取り入れてみよう」
そんな気持ちで、少しずつ実践していきましょう!
叱らないために先生自身も大切にしてほしいこと

子どもを叱らない指導を続けていくには、実は「先生自身の心の余裕」が何より大切です。
毎日忙しく働き、たくさんの子どもたちと向き合う中で、
いつも冷静で優しくいられるなんて、正直なかなか難しいですよね。
だからこそ、まずは自分自身を大切にすることを、どうか後回しにしないでください。
例えば…
- 少しでもホッとできる時間を意識して作る
- 同僚や先輩に悩みを相談してみる
- 「今日はうまくできなかったな」と思う日も、自分を責めすぎない
- プライベートの楽しみを持つ
- 週末に好きなものを食べたり、体を休めたりする
こうした小さな自己ケアが、心のエネルギーを満たしてくれます。
先生自身が心に余裕を持って子どもたちと向き合えたら、
自然と「叱る」場面は減っていきます。
子どもたちもまた、先生の温かいまなざしを感じて、安心して行動できるようになるでしょう。
完璧を目指さなくても大丈夫。
大切なのは「毎日少しずつ、自分も子どもも認めていくこと」です。
子どもにとって「やさしい先生」になれるかどうかは、
まず先生自身が、自分にやさしくできるかどうかにかかっています。
焦らず、自分のペースで。
あなた自身も、大切な存在なのですから。
【まとめ】「やさしい先生」は、今日から一歩ずつつくれる
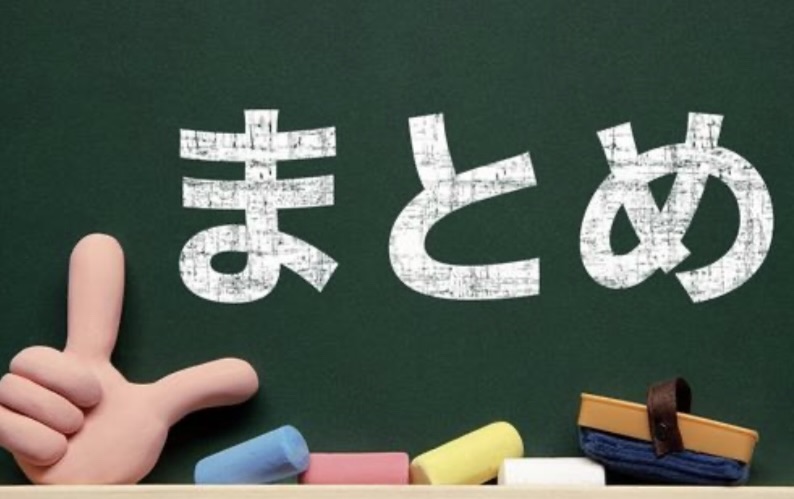
「やさしい先生になりたい」と思う気持ち、
その思いがすでに素晴らしい一歩です。
完璧な指導も、ミスのない声かけも、最初からできる必要はありません。
大切なのは、子どもたち一人ひとりの心に寄り添う姿勢。
叱る前に深呼吸して、少しだけ違う角度から子どもを見てみる。
できたこと、小さな成長を見つけて、そっと認めてあげる。
その小さな積み重ねが、子どもたちとの信頼関係を育て、
「やさしい先生」へと自然につながっていきます。
たとえうまくいかない日があっても大丈夫。
子どもたちは、あなたの完璧さではなく、
向き合おうとする姿をちゃんと見ています。
今日、ほんのひとつだけでも。
叱る前に「どうしたのかな?」と声をかけてみる。
失敗しても、「チャレンジしたね!」と認めてあげる。
そんな小さな実践が、あなた自身も、子どもたちも、少しずつ変えていきます。
焦らず、比べず、自分らしい「やさしい先生」への道を歩んでいきましょう。
あなたの「やさしさ」は、きっと、誰かの未来を変える力になるはずです。