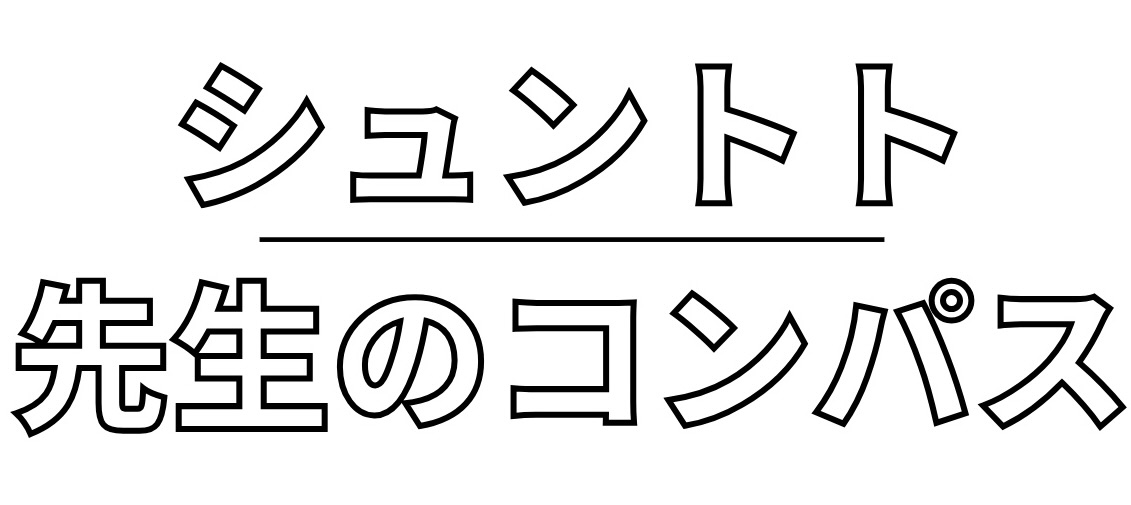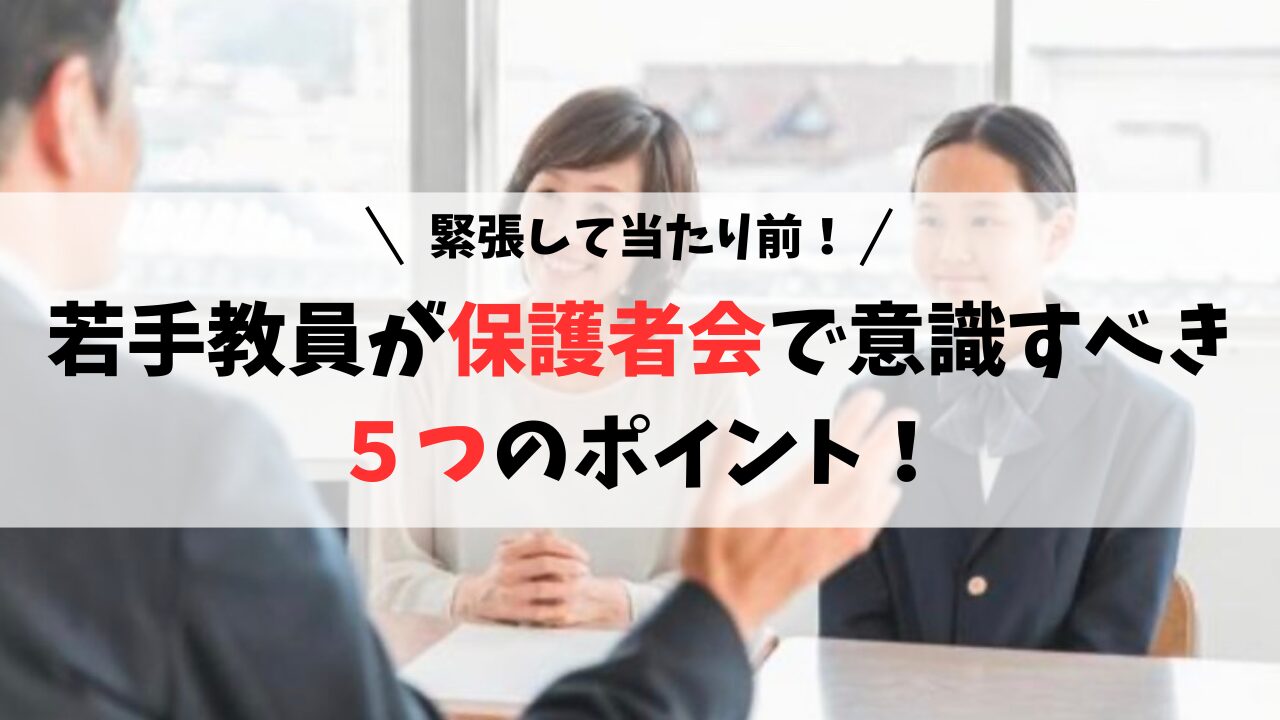目次
はじめての保護者会。
教室の空気、保護者の視線、言葉の選び方…。
考えれば考えるほど、不安になってしまう若手の先生も多いのではないでしょうか。
でも、大丈夫です!
保護者会で大切なのは、「上手に話すこと」ではなく、「誠実に伝えること」。
保護者は完璧なプレゼンを求めているわけではありません。
先生としての本気や真剣さが伝われば、それが信頼につながります。
この記事では、若手教員が保護者会で押さえるべき準備・話し方・当日の心構えなどを、わかりやすく解説します!
自己紹介は「親しみ」と「安心感」を意識して

初めての保護者会。
教室に入ってきた保護者の方々を前にすると、つい緊張してガチガチになってしまうものです。
でも、保護者の方もきっと同じ。
「どんな先生なんだろう?」「うちの子をちゃんと見てくれるかな?」と、
少なからず不安や期待を抱えて参加されています。
そんなときこそ、自己紹介で大切にしたいのが「親しみ」と「安心感」!
難しい言葉や完璧なスピーチなんて必要ありません。
むしろ、少し緊張しているくらいの姿の方が
「誠実そう」「一生懸命な先生」と好印象につながることも多いんです。
たとえばこんな工夫がおすすめです。
- 名前だけでなく、「どう呼ばれているか」や「自分のキャラ」を伝える
→「子どもたちからは〇〇先生って呼ばれてます」
などの一言で、ぐっと距離が縮まります。 - なぜ教員を志したか、どんな学級にしたいかを素直に語る
→「子どもたちが毎日学校楽しい!と言えるようなクラスにしたいと思っています」
といった言葉が、保護者の信頼につながります。
・完璧な先生であろうとしない
→「まだまだ若輩者ですが、お子さんたちと一緒に日々学びながら進んでいきます」
と伝えることで、一緒に育てていくという温かい関係性を築く第一歩になります。
一番大事なのは、「この先生に任せても大丈夫そうだな」と思ってもらうこと!
そのためには、形式ばったスピーチよりも、あなたらしさが伝わる言葉が何よりの信頼を生むのです。
(伝え方の参考になる書籍はこちら👇)
「家庭との連携」を伝える言葉を意識しよう

保護者会では「学校での様子を伝えること」に意識が向きがちですが、
それと同じくらい大切なのが、「ご家庭との連携を大切にしています」という姿勢を伝えることです。
若手の先生にありがちなのが、「こちらから伝えること」に精一杯になり、
つい一方的な話し方になってしまうこと。
でも保護者にとっては、
「この先生は、家庭のことにも耳を傾けてくれそうだな」
と思える一言があるだけで、グッと安心感が高まります。
たとえば…
- 「学校での姿はこうでしたが、お家ではいかがですか?」
- 「お子さんのいいところを、これからも一緒に伸ばしていきたいです」
- 「家庭と連携しながらサポートしていけたらと思っています」
といった言葉を加えるだけで、グッと信頼感のある話し方になります!
また、家庭と学校がチームであることを伝えることで、保護者の協力も得やすくなります。
「一緒に育てていく」という意識を持っている先生は、それだけで保護者にとって心強い存在です。
(伝え方の参考になる書籍はこちら👇)
子どもの「良いところ」を具体的に伝える

「うちの子、ちゃんとやってますか?」
「迷惑かけてませんか?」
保護者会でよく聞かれる質問ですが、これは保護者の心配が言葉になっているもの。
特に若手教員の場合、責められているように感じて焦ってしまうこともあるかもしれません。
でも、そこで慌てずに、お子さんの「良いところ」をひとつでも伝えることができれば、
それだけで場の雰囲気はぐっと和らぎます。
たとえば、
「授業中の挙手はまだ少ないですが、ノートをしっかり取っているのが印象的です」
「お友達にやさしく声をかけている姿をよく見かけます」
といったように、その子が努力している姿や、
日常のちょっとした素敵な場面を言葉にして伝えることで、保護者に安心してもらえるのです。
完璧な報告をする必要はありません。
大切なのは、「ちゃんと見てくれているんだな」と保護者に感じてもらえること。
たとえ小さな変化や取り組みでも、それを丁寧に伝えることで、
子どもに対する信頼感が生まれ、家庭との連携もしやすくなっていきます。
(伝え方の参考になる書籍はこちら👇)
「伝える」より「聴く」姿勢を大切に

保護者会というと、
「何を話そう?」「うまく説明できるかな?」
と、話す内容にばかり意識が向いてしまいがちです。
でも実は、「伝えること」以上に大切なのが、「聴く姿勢」なんです。
保護者の方々は、子どもに関する悩みや不安、
ちょっとした質問や相談を胸に抱えて参加されています。
そんなときに、先生が一方的に話すだけでなく、
相手の言葉に耳を傾ける姿勢があることで、
「この先生になら安心して任せられる」と信頼を深めてもらえます。
特に若手の先生の場合、緊張から話すことに必死になってしまうのも当然。
でも、ほんの少しの相づちやうなずき、
目を見て聞くといった丁寧なコミュニケーションだけでも、
保護者との距離はぐっと縮まります。
また、「ご家庭ではどうですか?」「何か気になることはありますか?」
と、質問を投げかけるだけで対話のきっかけが生まれます。
これは、家庭と学校が協力し合う関係性を築くうえでも大切なステップ。
つまり、保護者会は「情報を一方的に伝える場」ではなく、
「保護者と一緒に子どもを育てていくためのスタート地点」。
だからこそ、聴く力が信頼関係の土台になります。
【まとめ】保護者会は「信頼を築く第一歩」

保護者会は、ただの説明の場ではなく、
保護者との信頼関係を築く貴重な時間です。
特に若手教員にとっては、
「子どもたちのことを共に支えるチームの一員として認めてもらう大切な場」
とも言えます。
はじめての保護者会では、緊張するのは当然のこと。
ですが、次のようなことを意識するだけで、ぐっと印象が変わります。
- 専門用語を避け、わかりやすい言葉で伝える
- 子どもの様子を具体的に伝える(エピソードがあると効果的)
- 保護者の不安に寄り添う姿勢を見せる
- 「一緒に育てていきましょう」という協力的なスタンスを忘れない
また、話す内容だけでなく、
表情や声のトーン、うなずきなどの非言語コミュニケーションも、
保護者に安心感を与える大きな要素になります。
何より大切なのは、
「完璧にやろう」と気負うことではなく、誠実に、真摯に保護者と向き合う姿勢です。
その姿こそが、子どもを預ける立場の保護者にとって一番信頼できる要素となります。
若手教員だからこそ、子どもたちへのまっすぐな思いや、
保護者としっかり向き合おうとする姿勢が伝わります。
小さな一歩を積み重ねながら、経験を糧に、
より良いコミュニケーションを築いていきましょう。
これからの保護者会が、先生自身の成長と、
子どもたちのより良い学びの土台になることを願っています。