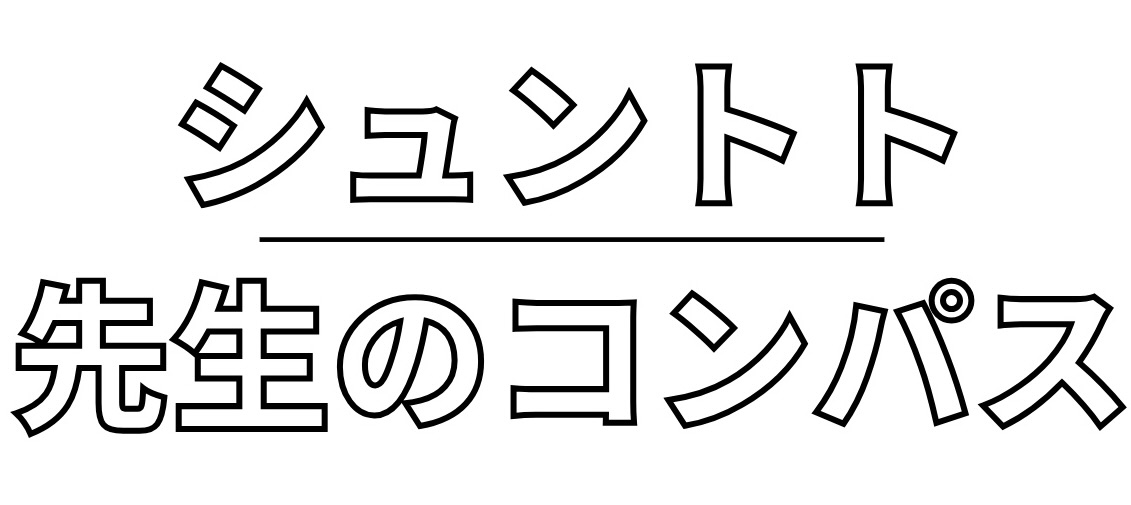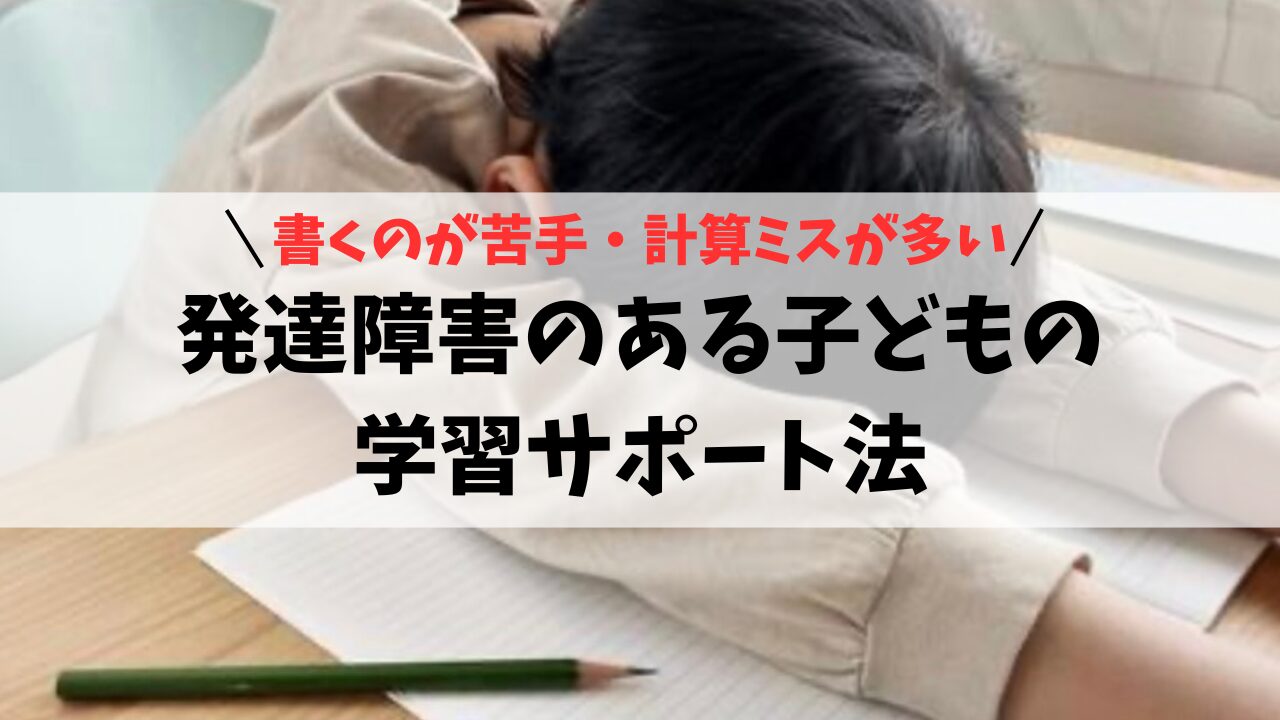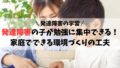目次
「どうして何度も同じミスをするの?」「もっと丁寧に書けばいいのに…」
そんなふうに思ってしまうこと、ありますよね。
でも、お子さん自身も「うまくできないこと」に悩み、困っているかもしれません。
発達障害(ADHD・ASD・LDなど)の特性によって、「書く」「計算する」といった学習の基本動作が苦手になることがあります。
この記事では、そんな子どもたちの困りごとに家庭でできるやさしいサポートについてご紹介します。
無理なく、でも確実に「できた!」を増やしていくヒントになれば嬉しいです。
「書くのが苦手」「字が雑」…その子の中で何が起きている?
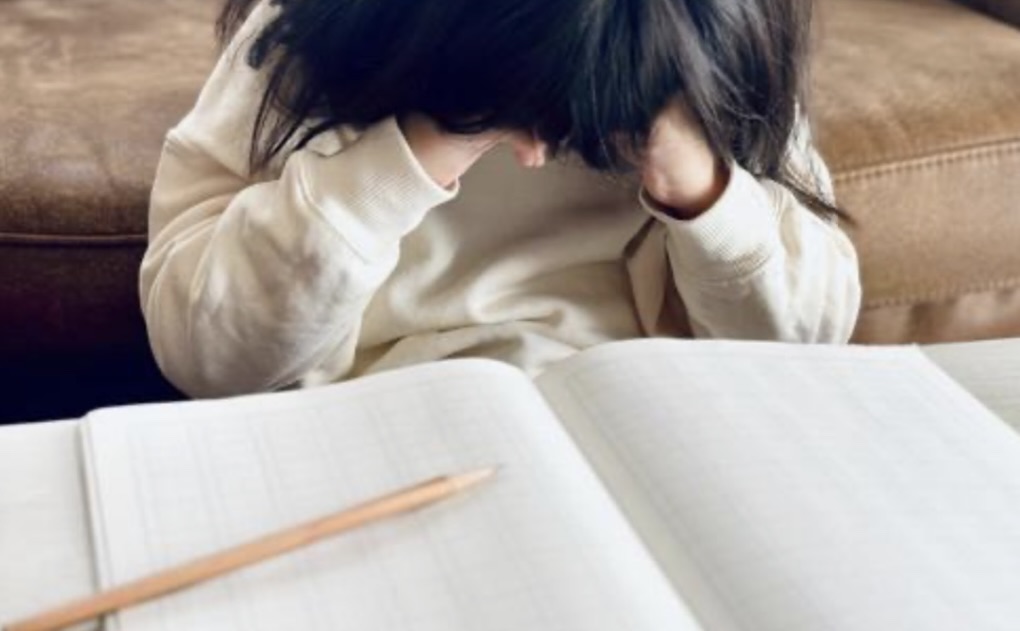
「もっと丁寧に書いてね」「もう少し綺麗に書けるはず」
そんなふうに声をかけたくなる場面、きっとあると思います。
でも、お子さん自身も「うまく書けないこと」に、モヤモヤやイライラを感じていることが多いんです。
実は、「書くのが苦手」というのは、単なる“字が汚い”という話ではなく、見え方・感じ方・動かし方など、いろいろな要素が関係していることがあります。
たとえば…
- 視覚認知のつまずき → 書く位置がズレたり、形を覚えるのが難しかったりします
- 手や指の動きに不器用さがある → 力加減がうまくできず、すぐ疲れてしまうことも
- 気が散りやすく集中が続かない → 書いているうちに違うことに気を取られてしまうこともあります
ADHDの特性で注意がそれやすかったり、LD(学習障害)による書字の困難さ、ASDの感覚のこだわりなど、「書くことが苦手」な理由は一人ひとり違います。
大切なのは、「なぜうまく書けないのかな?」と、その子の視点に立ってみること。
「丁寧に書きなさい」よりも、「どうしたら書きやすくなるかな?」というサポートのほうが、子どもにとっても前向きな一歩になります。
計算ミスが多いのはなぜ?ミスを責めないサポートを

「また間違えたの?」「なんでこんな簡単な計算でミスするの…」
そんなふうに言いたくなる気持ち、親としてとてもよく分かります。
でも、実はそのよくあるミスの裏には、子ども本人も気づいていない特性や困りごとが隠れていることがあります。
たとえば、ADHDの傾向がある子は、集中力が続きにくく、問題の読み飛ばしや計算過程の省略をしてしまうことが多いです。
また、ワーキングメモリ(作業記憶)の弱さがあると、途中の計算式や数値を頭の中で保持するのが難しく、ステップを飛ばしてしまうこともあります。
でも、ここで大切なのは「なぜできないのか?」ではなく、「どうすればできるようになるのか?」に目を向けることです。
ミスを責めるのではなく、「どこでつまずいたのかな?」「どうしたらやりやすくなるかな?」と一緒に考える姿勢が、子どもにとって大きな安心感につながります。
また、ケアレスミス防止のチェックリストを作る、問題用紙に定規や下敷きを使って視線を固定するなど、具体的なサポートが効果的なこともあります。
ときには、計算式を声に出して読んだり、書きながら確認する「ダブルチェック法」も、ミスを減らす手助けになります。
子どもが間違えてしまったときほど、
「ミスは成長のヒント」だと捉えて、親が一緒に歩んでいく姿勢を持つことが何よりも大切です。
家庭でできる!書く力・計算力を伸ばす工夫

「うちでも何かできることがあれば…」
そう感じているママやパパにこそ、家庭だからこそできるちょっとした工夫を取り入れてみてほしいと思います。
たとえば「書くのが苦手」なお子さんの場合、
いきなりノートにたくさんの文字を書かせようとすると、手が疲れたり、字を丁寧に書こうとする余裕がなくなってしまうこともあります。
そこでおすすめなのが、マス目の大きいドリルや、1ページに少しずつ取り組めるワークブック。
「できた!」という達成感が得られやすく、自然とモチベーションも上がっていきます。
また、鉛筆の持ち方や筆圧に課題がある場合は、グリップ付きの鉛筆や、書きやすい三角鉛筆など、
手に合った文具を取り入れるだけでもストレスが減ることがあります。
「計算が苦手」「数の概念がつかみにくい」というお子さんには、具体物を使った学習がとても有効です。
たとえば、おはじきや積み木を使って数を目で見て確認する。
実際に手を動かしながら計算の意味を体感できるので、数への理解が深まりやすくなります。
さらに、家庭学習で取り入れやすいのが、短時間のスモールステップ学習です。
「今日はここだけ頑張ろう」「1問だけでもOK」と小さな目標をクリアしていくスタイルなら、集中力が続かないお子さんでも取り組みやすく、自信にもつながります。
どの工夫も、「うまくできたね」「がんばったね」と親があたたかく声をかけてあげることが何よりのサポートになります。
「できない」ではなく、
「できるようになるための方法を一緒に探す」それが、家庭での支え方の第一歩です♪
声かけと環境づくりで“やる気”を引き出す

お子さんが「やる気を出してくれない…」そんなとき、つい「もっとちゃんとやって!」「なんでできないの?」と声を荒げてしまった経験、ありませんか?
でも実は、子どもたちはやる気がないのではなく、やる気の出し方がわからないだけということも多いのです。
まず大切なのは、お子さんのできたをしっかり言葉にして伝えてあげること。
たとえ小さなことでも、「今の字、いつもより読みやすかったね!」「この計算、前より速くなったね!」といった前向きな声かけが、お子さんの自己肯定感をぐんと育ててくれます。
また、「勉強しなさい」という言葉は逆効果になることも…。
それよりも、「一緒に5分だけやってみようか?」「この問題、ママもやってみていい?」など、
親が伴走者として寄り添う姿勢を見せることで、自然とお子さんも机に向かいやすくなります。
環境づくりもやる気を引き出す鍵のひとつ。
たとえば、テレビやおもちゃが視界に入らないようにしたり、学習専用のスペースを用意したりと、
集中しやすい空間を整えてあげることがポイントです。
中には、「学習スペースがない」というご家庭もあるかと思いますが、ダイニングテーブルの一角に学習マットを敷くだけでもここは勉強する場所と意識づけができるのでおすすめです。
また、学習時間を「ごはんのあと」「お風呂の前」など、生活の中に自然に組み込むことで習慣化につながることもあります。
決して長い時間でなくていいんです。毎日ちょっとずつの積み重ねが、やる気と自信を育てていきます。
お子さんのやる気は、強く言い聞かせるのではなく、
「認めてもらえた」「一緒に頑張ってくれる人がいる」と感じたときに、そっと芽を出します♪
おすすめの学習ツール・教材【発達特性に合わせて選ぼう】

発達障害のお子さんには、「自分に合った学び方」や「使いやすいツール」がとても大切です。
「書くのが苦手」「計算に時間がかかる」「集中が続かない」など、特性によってつまずき方はそれぞれ違いますよね。
だからこそ、お子さんの得意・不得意をよく観察して、それに合った教材やサポートグッズを選んでいくことがポイントになります。
書字サポート系
- 【ポスカノート】…大きめマス&ガイド付きで書きやすい
- 【ユニバーサルデザインノート】…視認性が高く、書き取りに最適
デジタル教材
- 【すらら】…無学年式、視覚・聴覚どちらにも対応した教材(LDやASDの子に人気)
- 【RISU算数】…個別AI指導型のタブレット学習。計算ミスに対するフィードバックが細かい
その他の便利アイテム
- タイマー(時間の見える化で集中力UP)
- 指マーカーや定規(視覚のガイドとして活用)
何より大切なのは、「他の子と同じじゃなくていい」とお子さん自身が感じられること。
教材やツールは本人が気に入って、続けられるかどうかがいちばんの基準です。
高価なものでなくても、「これならやってみたいな」と思えるものを一緒に選んであげてくださいね♪
おわりに|「できない」ではなく、「どう支えるか」を一緒に考えていこう

「書くのが苦手」「計算ミスが多い」そんなお子さんの姿を見て、親として不安になったり、心配になったりすること、ありますよね。
でも、それは決してダメなことではなく、その子が持っている特性や困りごとがちょっと目に見えているだけなのかもしれません。
大切なのは、「どうしてできないの?」ではなく、「どうしたらその子に合った方法でできるようになるかな?」と視点を変えてみること。
完璧なサポートなんて、誰にもできません。
でも、お子さんの困りごとに気づき、向き合おうとするその姿勢こそが、何よりの力になるんです。
学習がうまくいかない原因は、「やる気がない」からではなく、環境や方法が合っていないだけということがほとんど。
だからこそ、少しの工夫やツールの力を借りるだけでも、大きな変化が生まれます。
焦らず、比べず、その子のペースで。
今日のひとつの声かけ、今日のひとつの工夫が、きっと明日へつながっていきます。
一緒に、小さな「できた!」を積み重ねていきましょう♪
お子さんの笑顔も、保護者であるあなたの安心も、どちらも大切にできる学びの環境を、これから一緒につくっていけますように。